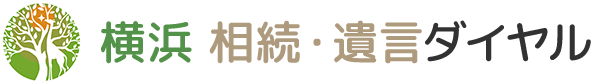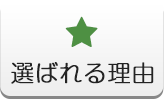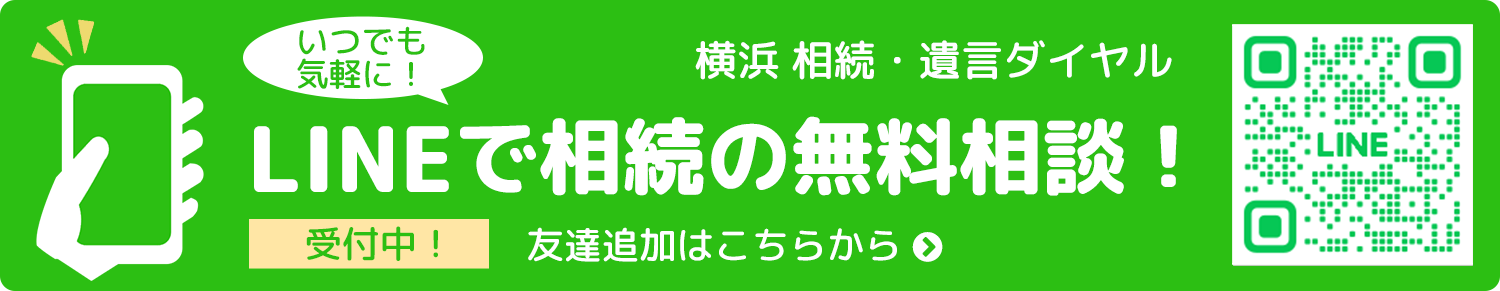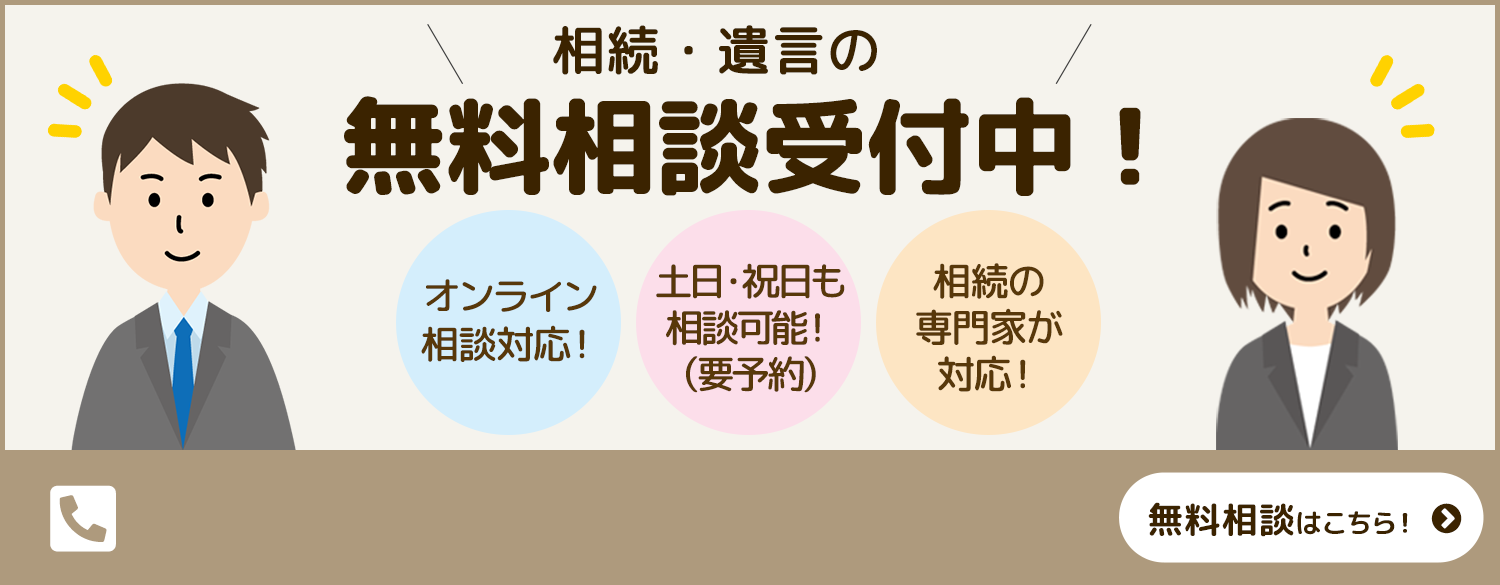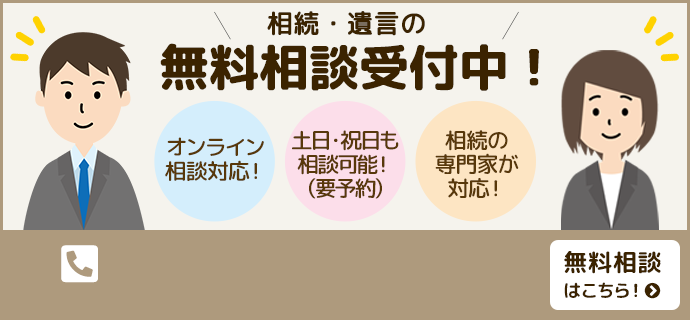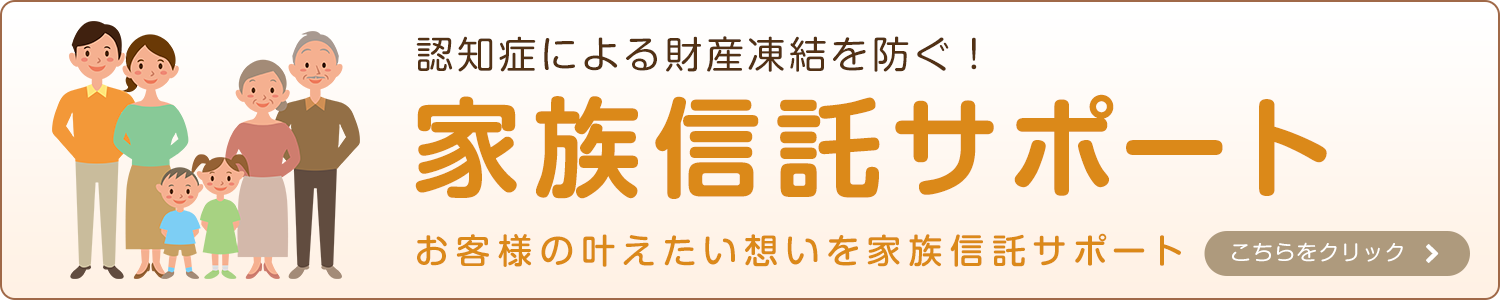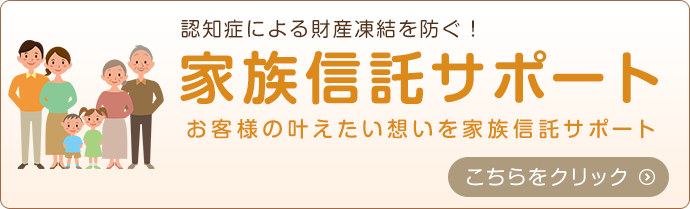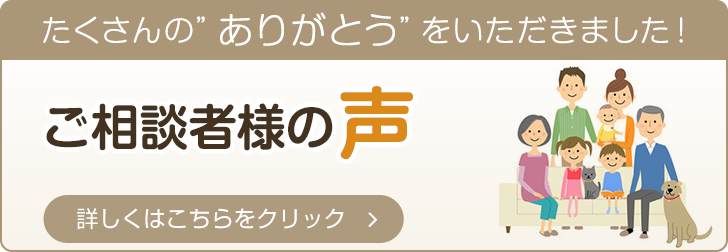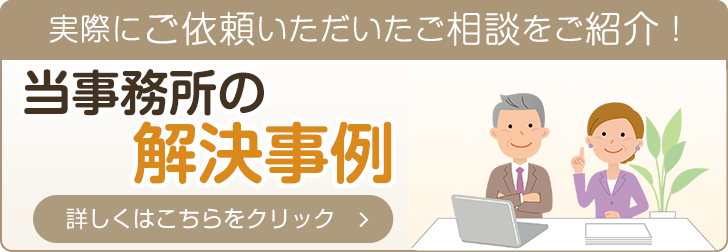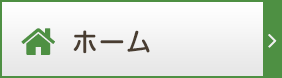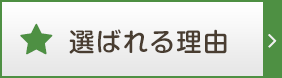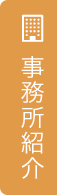【司法書士が解説】自筆の遺言書が相続手続きに使えなかったケース|解決事例
1. お客様のご状況
Aさんからご相談いただきました。
Aさんの母Bさんが亡くなりました。相続人は亡Bさんの長女であるAさんと、次女のCさんです。
亡くなったBさんは自筆の遺言書を作成していました。Aさんが発見し、家庭裁判所で検認の手続きを受けて開封したところ、財産をすべてAさんに相続させると書かれていました。
そこで、当事務所に自宅の相続登記を依頼したいと遺言書を持参してご相談に来られました。
【被相続人=亡くなった方】
・Bさん
【相続人】
・Aさん(長女)
・Cさん(次女)
【財産状況】
・不動産(自宅)
・預貯金
2. 当事務所からの提案&お手伝い
遺言書を確認したところ、Bさんの署名がありませんでした。民法では、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付、及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。」と定められています。署名がない場合は遺言書は有効とはならず、相続手続きで使用できません。遺言書の検認は、遺言書の形状や日付、署名等の内容を明確にし、偽造や変造を防止するための手続きであり、検認を受けているからと言って遺言書が有効というわけではないのです。結局、AさんとCさんで遺産分割協議書を作成して相続手続きを行うことになりました。
当事務所では、以下のサポートを行いました。
1. 戸籍謄本等チェック
2. 相続関係説明図(家系図)作成
3. 遺産分割協議書作成
4. 相続登記申請
3. 結果
Aさんがすべての財産を取得する内容の遺産分割協議が成立し、自宅をAさんの名義に変更することができました。Aさんは、遺言書の検認を受けていても遺言書が有効であるとは限らないと知り、とても驚いていらっしゃいましたが、無事に名義変更手続きが済み、安心されたご様子でした。
せっかく遺言書を作成するのなら、内容が有効となるよう、しっかりと専門家に相談しましょう。しかし万が一遺言書が有効でなくても、解決方法はありますのでご安心ください。
当事務所では相続の無料相談を実施中です!
 当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。
当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。
相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。
お電話もしくはLINEよりお問い合わせください。
TEL:0120-073844
相続の専門家が丁寧な面談を実施します。お気軽にご相談ください。