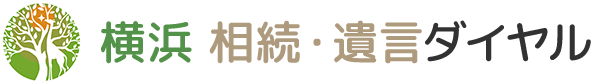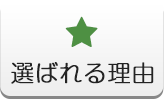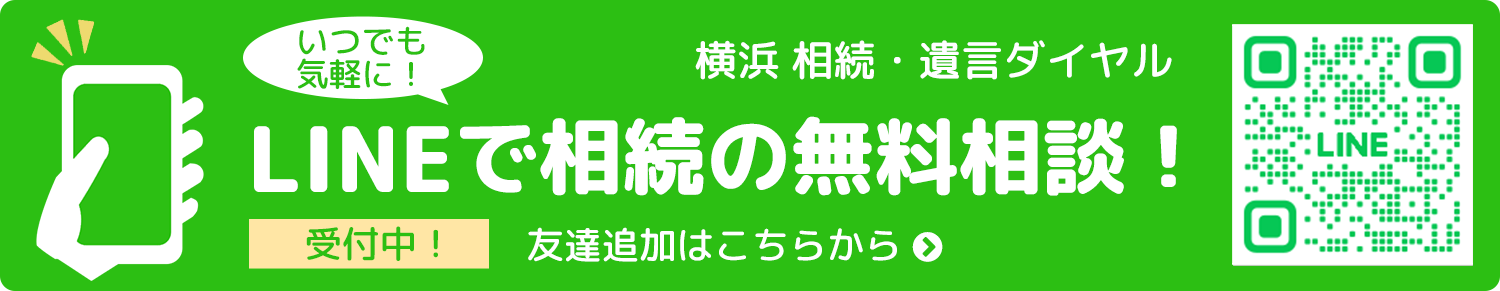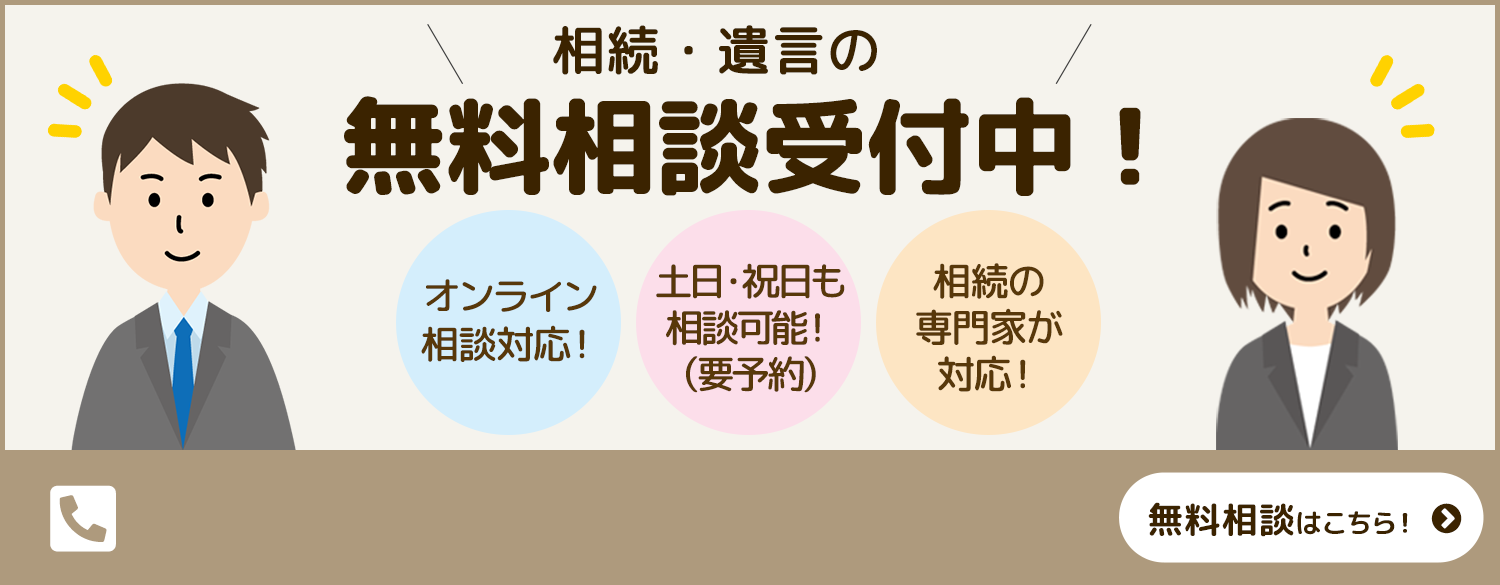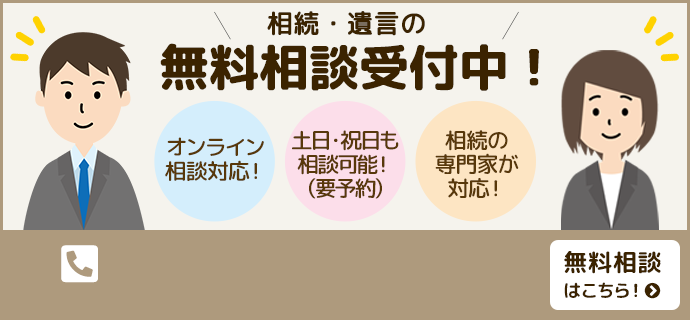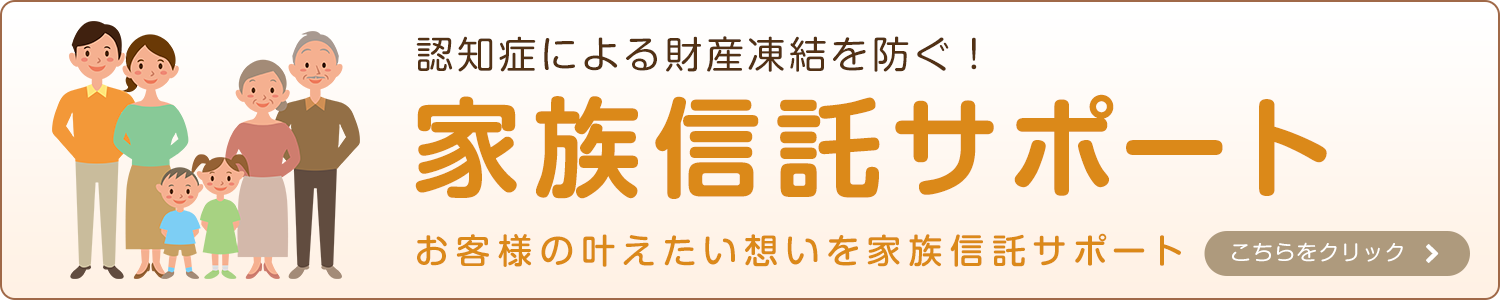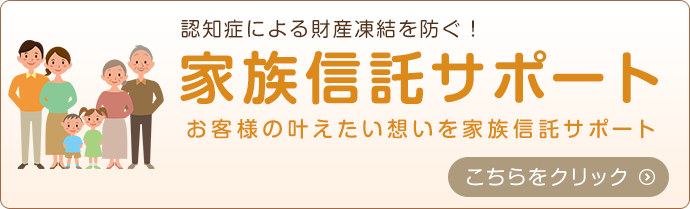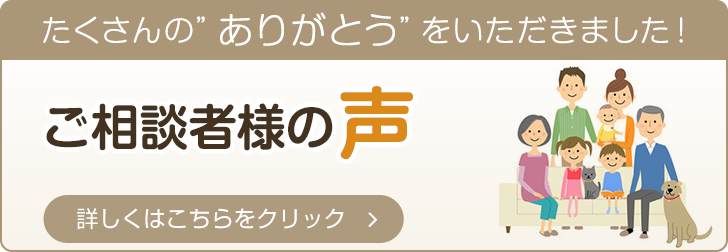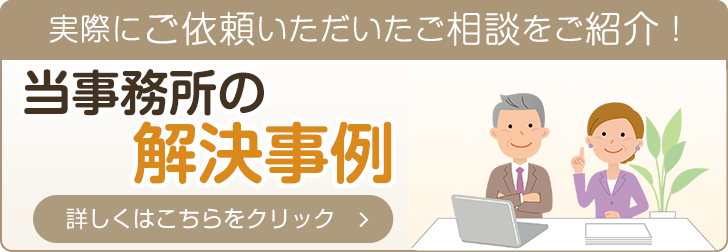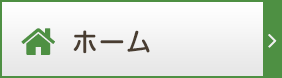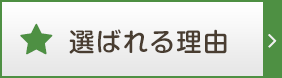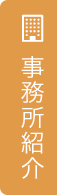【司法書士が解説】遺言で指定された相続人が先に死亡…予備的相続人も死亡していた場合の遺産のゆくえ」|解決事例
1. お客様のご状況
Aさんからご相談いただきました。
Aさんの祖母Xさんが亡くなりました。亡くなったXさんの遺言書には、Xさんの子供たち4名それぞれに相続させる財産が指定されていました。Aさんの父・BさんはXさんの三男であり、Bさんには不動産を相続させると記載がありました。また、「もしBが先に死亡していた場合は、Bの妻Cに相続させる」と予備的な相続人の指定もありました。
しかし実際には、Xさんの死亡時点でBさんもCさんもすでに亡くなっており、遺言の内容が実行不可能な状況となっていました。
【被相続人=亡くなった方】
・Xさん
【相続人】
・Dさん(長男)、Eさん(長女)、Fさん(二男)、Aさん(三男である亡Bさんの長女)
2. 当事務所からの提案&お手伝い
Xさんの遺言書は、Dさん、Eさん、Fさんを相続人と指定する部分については有効ですが、亡Bさん、予備的に亡Cさんを相続人と指定する部分については無効となります。
そのため、無効となっている部分については相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。法定相続人を確定するための戸籍調査から遺産分割協議書の作成、相続登記申請までワンストップで当事務所で進めることをご提案しました。
当事務所では下記のサポートを行いました。
1. 遺言書のチェック
2. 戸籍謄本等の取得
3. 相続関係説明図、遺産分割協議書作成
4. 相続登記申請
3. 結果
相続人全員による遺産分割協議が成立し、無事に不動産の相続登記が完了。実行不能な遺言に縛られず、法定のルールに従って円満に相続を終えることができました。
4.司法書士からひとこと
予備的遺言とは、「指定した相続人や受遺者が遺言者の死亡時にすでに死亡している」などの事態に備えて、別の者に相続や遺贈をする内容の遺言をいいます。たとえば、「長男Aに全財産を相続させる。もしAが先に死亡していた場合は、長女Bに相続させる。」
というように、第一順位と第二順位の受遺者・相続人を指定する形式です。
予備的遺言は実務でもしばしば用いられており、明確な意思表示がある場合は民法の趣旨に沿って解釈されます。
しかし、予備的遺言にも限界があり、予備的に指定された受遺者・相続人も死亡していた場合、遺言は効力を失い、法定相続に移行することになります。
遺言は“未来への指示書”ですので、定期的な見直しがとても大切です。少しでもご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。
当事務所では相続の無料相談を実施中です!
 当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。
当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。
相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。
お電話もしくはLINEよりお問い合わせください。
TEL:0120-073844
相続の専門家が丁寧な面談を実施します。お気軽にご相談ください。